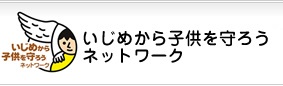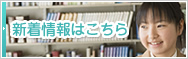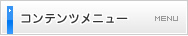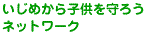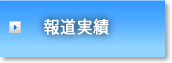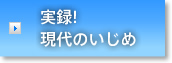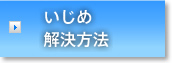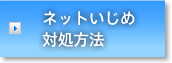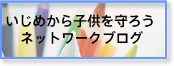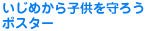今月の代表メッセージ
12月の代表メッセージ
☆2025年12月18日☆
[いじめから子供を守ろう メールマガジン]
◇ 代表メッセージ ◇
■□ 「愛ある視線」で子供たちを見守りたい □■
スキー場もオープンしましたし、冬ですね。
気象庁によると、今年の冬は、「冬の気温は、全国的にほぼ平年並の見込みで、
冬の降水量は、東日本日本海側で平年並か多いでしょう。」とのことですので、
冬らしい冬になりそうです。
「寒いな」と思っていると、ふと、「子供は風の子」という言葉が浮かんできました。
懐かしい言葉ですが、都市部ではすでに死語扱いされてるような気もします。
子供たちに、元気に冬を楽しんでもらいたいものです。
さて、12月に入って、高知県の小学校教員採用試験の合格者のうち約6割もの人が
辞退したというニュースが流れてきました。
12月4日の朝日新聞の記事を引用いたします。
—–
県教委によると、1次試験は5月末に高知市と大阪府の会場で実施し、計468人が受験した。
辞退者らを見込んで採用予定の2倍の260人を合格とし、9月に通知したが、
12月3日までに61.5%にあたる160人が辞退したという。(中略)
県では昨年、25年度採用の合格者の約7割が辞退、
12月の追加選考などを経て春採用の129人を確保した。
24年度採用分でも約7割が辞退していた。
——
高知県だけでなく、近年は全国的に教員不足が加速しているようです。
特に長時間労働の改善が進まないことなどが背景にあるという見方をしている方もいらっしゃるようです。
教員不足の現状について、耳に入ってくる情報では、
教員になってもすぐに辞められる方や心身の不調に陥る方がかなり多いと聞きます。
統計上のことは分かりませんが、先生方もこのことに強い危機感を持っていらっしゃいます。
教師という職業、さらには「教育」に生きがいを感じない社会風潮が強くなっているように見えます。
禅の言葉で、「そっ啄同時(そったくどうじ)」という言葉があります(そつは口偏に卒)。
広辞苑によりますと「そつ」は鶏の卵がかえる時、殻の中で雛がつつく音、
「啄」は「母鶏が殻を外からつつき破ること」が同時に起きる様を言います。
この雛と親鳥の呼吸が合わないと雛は卵を割って外に出ることができないという意味になります。
先生方は、この言葉を何度も耳にしたことがあるはずです。
子供たちが自ら成長していかんとする姿、
そして、子供らの成長を導く教師の姿は美しいものです
残念ながら、「人を育てる喜び」に価値を見いだしている教育者が
少なくなっていることに、寂しさを感じます。
先に述べたように、教員採用試験の辞退者が増えている理由に、長時間労働もあげられています。
確かに、部活や採点などでかなりの時間がとられています。
しかしながら、それ以上の価値があるはずです。
その価値のために、多くの方が教師を志し、
そして現在も教職についているのではないでしょうか。
また、こども家庭庁と文部科学省は、11月21日に、
「令和7年1月より、こども家庭庁及び文部科学省共同で
『いじめの重大化要因等の分析・検討会議』を開催し、
『いじめの重大化を防ぐための留意事項集』、
『いじめの重大化を防ぐための研修用事例集』を取りまとめましたので、公表いたします。」
として以下の文書を公開しました。
・「いじめの重大化を防ぐための留意事項集」
(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/235b378f-fa6a-4d86-9703-7d77004d6ce6/20d9a176/20251107_councils_ijime-judaikayoin_04.pdf)
・「いじめの重大化を防ぐための研修用事例集」
(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/235b378f-fa6a-4d86-9703-7d77004d6ce6/0fd2993e/20251107_councils_ijime-judaikayoin_05.pdf)
11月21日の北海道新聞は、
「いじめ重大化防止へ初の「留意事項集」 文科省・こども家庭庁 SNSなど把握難しいケース念頭」
という記事を掲載し、「留意事項の主なポイント」として、以下のようにまとめています。
—–
1.子供の「大丈夫」「何でもない」という言葉の裏に、
真に伝えたいことが隠れていないか立ち止まって考えることが必要
2.多様な背景の子供を受け入れるような学級づくりに取り組む
3.加害者の背景や事情を確認し、継続的に指導・支援する
4.親の情報提供で対応したことは、速やかに親に結果を伝える
5.修学旅行中や長期休暇明けは、子供同士の関係や孤立に配慮する
6.男女間トラブルや性的ないじめは、保護者はもとより警察と連携する
7.SNSなどで問題が生じた場合、大人に助けを求めるよう伝える
8.部活動など人間関係が固定されやすい集団は、いじめが重大化しやすい
—–
この文書は、教員の研修にも使われるのだろうと思います。
しかし、何よりも重要なことは、教員の子供たちに対する姿勢、考え方だと思うのです。
教員を志す人を増やすには、現職の先生たちが、
「教師」という職業に誇りや喜びを感じられるようにしていくことではないでしょうか。
文科省や教育委員会は、人を育てる責任や使命感にあふれた教師をつくり、育てることに注力することが、子供たちを社会に役立つ子に育てることになるはずです。
できる教師であれば、「留意事項」のポイントなど、特に意識しなくとも、
「留意事項」のポイントに沿った、子供たちへの接し方ができているように思います。
「愛」という言葉を使うと違和感があるかもしれませんが、
子供たちへの「愛」、時には厳しさを含んだ「優しさ」こそ、教師に求められる資質ではないでしょうか。
教師には「愛ある視線」が求められているのです。
冬です。年末です。冬休み、そしてクリスマス、お正月です。
先生方だけではなく、保護者の私たちも子供たちの言動に気を配ってまいりたいと思います。
何か気になることが発生しましたら、ご相談いただければ幸いです。
改めまして、本年も大変お世話になりました。心から感謝申し上げます。
良いお年をお迎えください。
一般財団法人 いじめから子供を守ろうネットワーク
代表 井澤一明