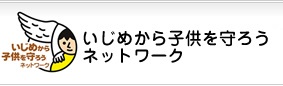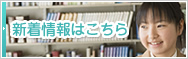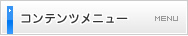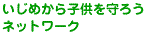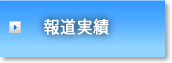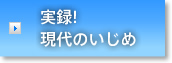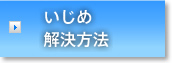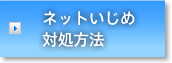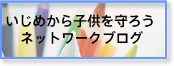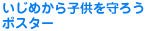今月の代表メッセージ
1月の代表メッセージ
☆2026年1月17日☆
[いじめから子供を守ろう メールマガジン]
◇ 代表メッセージ ◇
■□ いじめ動画事案は、傷害事件、犯罪と捉えるべき □■
遅くなりましたが、新年のご挨拶を申し上げます
2026年が皆様にとって素晴らしいお年となりますように
さて、1月4日に栃木の高校、8日に大分の中学校、続いて9日は熊本の中学校、10日に福井の高校。
この並びから、気付かれた方も多いと思いますが、
年明け早々、動画によっていじめ問題を告発する事件が相次ぎ、
報道でも大きく取り上げられています。
実際には何年か前の事件も含まれているようですが、
告発系のSNSのアカウントから、生徒同士のいじめや暴力行為が撮影された動画が、拡散され、
あわてて教育委員会がコメントを発表するなど対応に追われています。
最初の栃木県の高校の事件では、SNS上で動画が拡散されると共に、
「学校はこいつを退学にしてほしいな」
「こんなクズ共は許してはならない」
「警察や教師は役に立たない」
「社会的に抹殺すべし」
などのコメントが投稿される事態を招いています。
また、ネット上に加害者の生徒を特定する投稿が相次ぎました。
さらに、関係者でもないのに同校に押しかけたりする迷惑行為をする人間も出てきてしまいました。
この事件に対して同校の対応として1月9日の下野新聞では、
「暴行動画拡散の栃木県立高、防犯カメラ導入を検討 保護者会で校長が謝罪」
の見出しで伝えています。以下に一部引用いたします。
——-
栃木県立高の校内で生徒が別の生徒を暴行している動画が交流サイト(SNS)で拡散した問題を受け、
生徒が通う高校は9日夜、緊急保護者会を開き、校長が謝罪した。
現状の再発防止策と並行して、今後防犯カメラの導入などを検討することを明らかにした。
(中略)
今後、防犯カメラに加え、今回の問題で全国から抗議が相次ぐなどしているため、
部外者に対する生徒の安全対策として、入校証の発行の導入も検討する。
再発防止策として、昼休みなどに教職員が校内外の見回りを強化し、
交流サイト(SNS)などのリテラシー教育や相談しやすい学校の環境づくりにも取り組む。
登下校時の学校周辺警戒も当面の間続ける。
———
とのことです。
防犯カメラはやりすぎだとの意見もありますが、
いじめや暴力事件は、教師の目を避けて行われることが大半ですから、
死角をなくすための防犯カメラの設置もやむを得ないのではないでしょうか。
動画の事件ですが、一見、加害者は一人のように見えます。
私たちは2007年からポスターを学校に貼っていただいたり、
セミナーやシンポジウムなども開催しながら、
「いじめは犯罪!」という言葉を日本全国にひろめてまいりました。
悪口やからかい、無視のいじめも、大人が行えば明らかに「犯罪」だと主張し、
子どもたちに、いじめをやめようという運動をしてきたのですが、
今回の動画のような暴力事件は、犯罪ですし、
本来、110番通報すべき事件なのです。
マスコミも「いじめ」という言葉を使うことで、
「犯罪である」という認識から逃げているように見えます。
しかも、動画を録画している人間がおりますし、周囲には十人以上の生徒の姿も見えます。
これは「集団リンチ」ですし、「暴行事件」、「傷害事件」です。
くり返しますが、「犯罪」なのです。
被害者の立場にたてば、学生、生徒だから「配慮する」などという対応はなんの役にもたちません。
加害者は、罰すべきだとは思います。
1月16日には、保護者が被害届を出した熊本県の暴力事件で、
加害者の中学生が傷害容疑で逮捕されました。
当然の対応だと思います。
しかしながら「私刑」はあってはならないことです。
実名をさらしたり、個人情報をネットにあげたり、誹謗中傷を投稿したり、
これらの行為も犯罪なんだと認識していただきたいのです。
「アンガーマネージメント」という言葉もあります。
ぜひとも怒りを自重する努力をお願いしたいと思います。
さて、動画をあげる行為ですが、
被害者自身が動画を撮影しているわけはありません。
したがって、動画を投稿したアカウントの手に渡るにはいくつかのルートがあるはずです。
まずは、動画の撮影者が投稿した場合が考えられます。
動画撮影者、およびそこから動画を入手した者が、被害者に転送し、被害者が投稿したという場合も、
あるいは、動画撮影者から入手した人間が投稿した、などが考えられます。
動画投稿の理由としては、学校や教育委員会に訴えても何もしてくれないと悲嘆しての
「正義の告発」として世論の力を借りようとしたということもあるかもしれません。
学校や教育委員会の記者会見や、保護者会を開き、再発防止策を説明するなどの対応を見ると
学校に対応を促すという意味では成功したとも言えます。
また、加害者に報復したいという意味でも成果があったようにも見えます。
ですが、「正義の告発」ではなくて、
単に動画の再生回数を稼ぎたいとか広告収入を得たいなどの理由なら
あまりにも皮相です。
そんなことのために他人の悲劇を使ってほしくありません。
先程も述べましたが、学校が対応しない、学校が隠蔽する、学校が加害者を指導しないなどの
理由によって動画を投稿したということでしたら、ある程度は理解できます。
ですが、いきなりそこまで行くのではなく、もう少し他の手段もとってみませんか。
ということで、保護者の皆様に何点かの提案したいと思います。
まずは、110番通報です。
暴力に遭っている最中が一番効果的ですが、
現実には無理でしょうから、被害を受けた直後に110番です。
被害者であるにもかかわらず、「知られたくない」と思ってしまう子が多いのです。
この先入観をひっくり返すために、日頃から「そうではない。恥ずかしくない。被害者なんだ」と
「暴力を受けたら110番する」ように、お子さん方に伝えておいてください。
さらに、「教師や校長が、110番通報を制止しようとしても関係ないんだ、通報すること」と
教えておくべきです。
また、被害に遭ってしまったら、学校、教育委員会に通報すべきです。
と同時に、早急に医師に診断書を書いてもらいましょう。
さらに、状況が酷すぎるときには、すぐにでも警察に被害届を出すべきだと思います。
それでも何も進展しない、どうしようもないようでしたら、「動画を公開する」のではなく、
動画や診断書を持参して、新聞社やテレビ局の協力を得ることをお勧めいたします。
そして最終的には「動画を上げる」前に、弁護士に相談して訴訟を考えることなども、
検討していただきたいと思います。
それでもどうしようもないというのでしたら、
動画を通じて訴えることも一つの手段であるように思います。
ただ、子どもたちの顔にモザイク処理はすべきでしょう。
別の視点ですが、「周りの見ている子にいじめを止めさせるべき」という意見もよく見られます。
「いじめの四層構造論」には、
1.被害者、2.加害者、3.そしてはやし立てる観衆、4.さらに外からみている傍観者の
四者の存在が謳われています。
今回、動画にも、周囲に何人もの生徒の姿が見えました。
この「観衆」はほぼ加害者と言って良いではないかと思います。
一方、「傍観者」が教師や大人に助けを求めたり、「仲裁」あるいは
「制止」するような行動を起こすことを期待するのは、現在の状況では困難です。
そんなことをすれば、自分自身が被害者になってしまいます。
ですから「怖くてできない」というのが本音でしょう。
「通報したら学校が助けてくれる」ということが明確にならない限り無理なのです。
「あの先生なら助けてくれる」、「うちの学校では絶対に許さない」という生徒からの
信頼、信用を勝ち取れる学校をつくること。
このことを先生方や、校長は自覚し、その責任を果たしていただきたいと思います。
やろうと思えば、そのような正義にみちた学校はできるはずです。
今回は、簡単ですが対応方法について述べてみました。
皆様の周りで何か気になることがありましたら、今回のような騒動になる前に
一度、ご相談いただければ幸いです。
一般財団法人 いじめから子供を守ろうネットワーク
代表 井澤一明