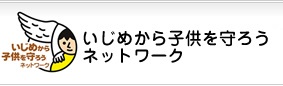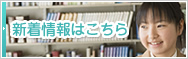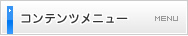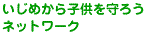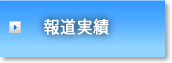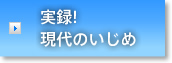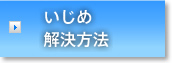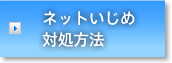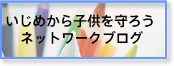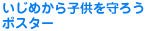2025年2月の代表メッセージ
2月の代表メッセージ
☆2025年2月18日☆
[いじめから子供を守ろう メールマガジン]
◇ 代表メッセージ ◇
■□ 裁判所が、加害者の別室指導を認めた □■
寒波到来の2月ですね。
雪の多いところでは大変な毎日が続いているようです。
早く、3月の春の日差しを浴びたいものです。
一方、学年末の3月になってしまうと、いじめの対応に学校が消極的になりやすい傾向があります。
3月を目前にして、いじめが続いている子にとっては正念場と言える季節です。
残された時間は多くないと考えて、積極的にアプローチしていくことが大切です。
さて、いじめ関連のニュースですが、
2月4日、Yahooニュースを通して 静岡放送の報道として、
「「重大事態に該当」学校法人側に賠償命じる 小学校”いじめ”対応めぐり」
という内容が掲載されました。
静岡市の私立小で、「重大事態」に該当するいじめであったにもかかわらず、
学校が調査しなかったのは違法であるとして、
被害者側が損害賠償を求めていた裁判で、静岡地裁が
学校法人に対し55万円の支払いを命じたという内容です。
以下に引用いたします。
——–
訴えによりますと、2021年1月、
学校の縦割り活動中に当時5年生だった男子児童の顔面に小学3年生の女子児童の足が直撃し、
永久歯が折れて不登校となり、その後、転校。
男子児童と両親はいじめ「重大事態」に該当することは明らかにもかかわらず
調査をしなかったのは違法だとして、学校法人に対し、損害賠償を求めていました。
静岡地方裁判所の平山馨裁判長は、
「原告の心身に重大な被害が生じた疑いがあると認められる重大事態に該当していた」とした上で
「調査を履行したものとは認められない」などとして請求通りの55万円の支払いを命じました。
———-
すでに何度かお伝えしておりますが、
私立の学校では、いじめが発生したときの対応が両極端になる傾向があります。
両極端というのは、
一方は、いじめ加害者に対して、ゼロトレランス(寛容さ無し)的な厳格な対応を行う学校であり、
もう一方は、徹底的に「いじめ隠蔽」を図る学校です。
私たちが相談にあずかったケースを見ると、
いじめを隠蔽する私立の学校では、周囲の保護者も隠蔽に加担する傾向が見られます。
全校をあげて隠蔽を図られると、包囲網を突破することはかなり困難です。
私立学校でのいじめ事件は、早めに外部の機関、場合に寄ってはマスコミに助けをもとめることを
考えていただきたいものだと思います。
また2月6日の朝日新聞には、
「高裁も維持した一審判決の「学習権侵害」認定 吹田市立小いじめ訴訟」
という記事がありました。
この事件は、
2018年度に、大阪府吹田市の市立小6の男子が、仲間外れなどのいじめを受け不登校になり、
修学旅行や卒業式にも参加できなかったとして、
被害者側が吹田市と同学年の加害者2人に計680万円の損害賠償を求めた裁判を起こしたものです。
当時、担任にはいじめの相談をしたが学校内で情報共有されず対応してもらえなかったといいます。
大阪地裁は2024年の5月16日、加害者への賠償請求は退けましたが、
吹田市に50万円の支払いを命じていました。
当時の産経新聞によりますと、
判決理由で、両親らに対し学校内で実施したアンケートに関する説明などが不十分だったとして、
学校側の過失を認定。
適切な対応があれば少年は教室に戻ることができたとし、
「教育を受ける権利が侵害された」と判断したとのことです。
この裁判の控訴審判決が2024年の12月にあり、
学校の対応を違法とした一審判決の判断を維持した上、
一審より10万円多い計60万円を男子児童と両親に支払うよう市に命じました。
吹田市は判決を不服として最高裁に上告受理申立をしました。
朝日新聞の報道を一部引用いたします。
——-
昨年5月の一審・大阪地裁判決は、
うわさをした同級生について把握した情報を母親に提供しなかったなどの学校の対応について、
「裁量を乱用または逸脱したもの」として違法と判断した。
男子児童は19年1月に登校を再開したが、うわさをした同級生がわからず
不安が解けなかったため、教室には復帰できないまま卒業。
違法な対応がなければ教室へ復帰できたとして、
学習権侵害を認め、慰謝料として50万円を払うよう市に命じた。
また、学校が男子児童側にアンケートの実施を事前に説明せず、内容への希望も聞かなかったことなど
アンケートの実施方法についても、文部科学省のいじめの重大事態の調査に関するガイドラインに違反し、
裁量を逸脱しており違法だとした。
——-
報道では、以下の点で重要な判断だと述べています。
1.教室で学習を受けられなければ、学習権侵害にあたると明示したこと
2.いじめ防止対策推進法と文科省のガイドラインをもとに学校側の対応を検討し違法と明示したこと。
3.同級生の名前など調査によってわかった事実関係は、
被害者からの要求がなくても学校が原告側に提供すべき情報に含まれると明示したこと。
4.うわさを言った同級生を別室学習とすることで男子児童が教室に復帰できたとしたこと。
いじめ事件が起きた際に、被害者が保健室登校となるケースが後をたちません。
これは学習権侵害になるという判断はとても重要だと言えます。
さらに被害者に別室学習を強いるのではなく、加害者を別室指導すべきだという点も重要です。
「いじめ防止対策推進法」には、いじめ被害者が安心して教育を受けられるよう、
加害者を別室で学習させる等の義務が定められているにもかかわらず、
実際に加害者を別室指導させる事例はほとんどありません。
裁判でこの点を明確に指摘したという点は特に評価できると思います。
全国の学校は対応を変えるべきです。
被害者を保健室ではなく、通常のクラスに通えるように配慮すること、加えて、
加害者に別室登校を促すことという、この2点の考え方を全国に浸透していただきたいものです。
ただ、残念なことがあります。
被害者に対しての賠償額があまりにも低いということです。
いじめの裁判において、賠償額があまりにも低すぎるのが日本の現状です。
今後、最高裁が高裁の判断を支持するかどうかを見守りたいと思います。
まもなく3月です。
いじめ問題では、極力、学年をまたいでしまうことを避けたいものだと思います。
不安に感じたり、気になることがございましたら、ご遠慮なくご相談いただければ幸いです。
一般財団法人 いじめから子供を守ろうネットワーク
代表 井澤一明